脳死臓器提供 家族の物語(上)価値観、共有していますか?残った人の為に
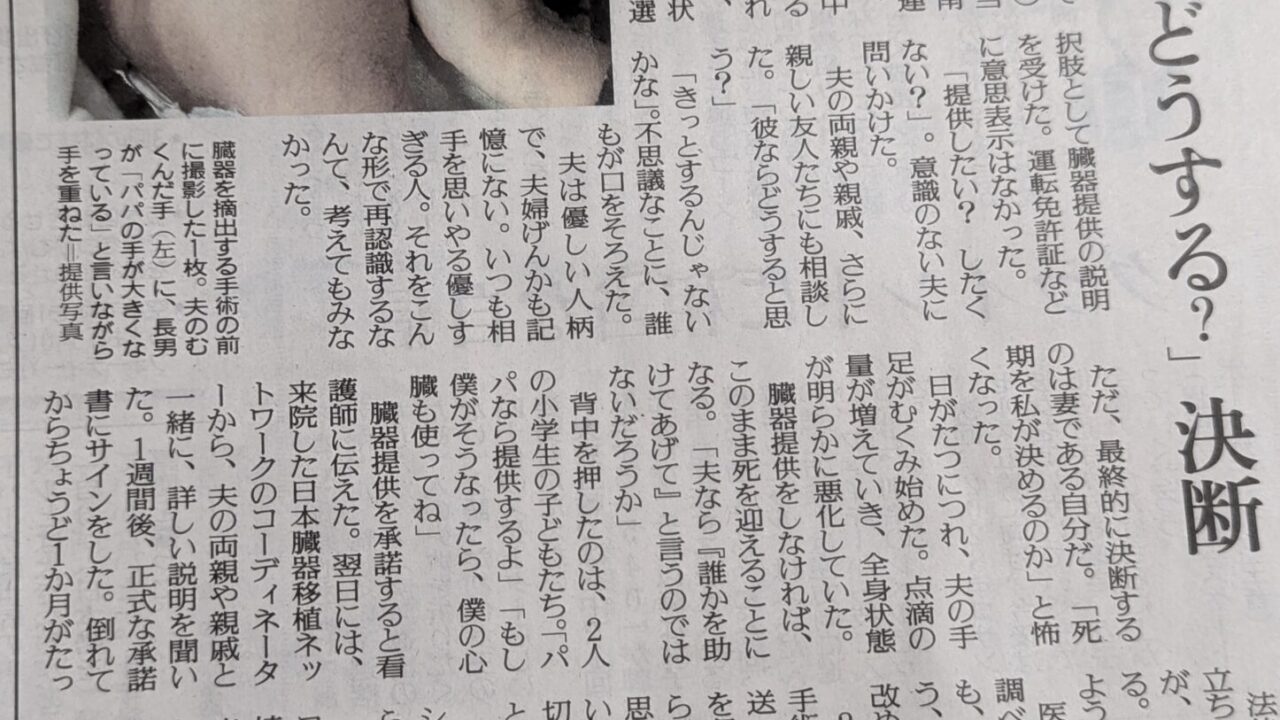
こんにちは。
8月8日(木)の読売新聞の記事で「脳死臓器提供 家族の物語」
「彼ならどうする?」決断より。
自分にも家族にも起こりえる、他人ごとでは無い内容でした。
原文そのままです。
自宅から山を越えて車で一時間。新潟県の女性(42)は、脳出血で倒れた夫(当時40歳)が入院する同県南魚沼市の魚沼基幹病院に連日通った。昨年のことだ。
人工呼吸器をつけ、集中治療室のベッドに横たわる夫の表情は穏やかで、触れれば温かい。医師からは回復の見込みのない脳死状態だと告げられている。
選択肢として臓器提供の説明を受けた。運転免許証などに意思表示はなかった。
「提供したい?したくない?」意識のない夫に問いかけた。
夫の両親や親せき、さらに親しい友人たちにも相談した。「彼ならどうすると思う?」「きっとするんじゃないかな」不思議なことに、誰もが口をそろえた。
夫は優しい人柄で、夫婦げんかも記憶にない。いつも相手を思いやる優しすぎる人。それをこんな形で再認識するなんて、考えてもみなかった。
ただ、最終的に決断するのは妻である自分だ。「死期を私が決めるのか」と怖くなった。
日がたつにつれ、夫の手足がむくみ始めた。点滴の量が増えていき、全身状態が明らかに悪化していた。
臓器提供しなければ、このまま死を迎えることになる。「夫なら『誰かを助けてあげて』というのではないだろうか」背中を押したのは、二人の小学生の子供たち。「パパなら提供するよ」「もし僕がそうなったら、僕の心臓も使ってね」
臓器提供を承諾すると看護師に伝えた。 翌日には、来院した日本臓器移植ネットワークのコーディネーターから、夫の両親や親戚と一緒に、詳しい説明を聞いた。 一週間後、正式な承諾書にサインをした。 倒れてからちょうど一か月がたっていた。
法律に基づく脳死判定に立ち会った。二回目の判定がそのまま死亡時刻になる。最期をしっかり見届けようと思った。
医師らが夫の目を開いて調べても、耳に水を入れても、全く反応はない。「もう戻らないんだな」と、改めて別れを実感した。
二日後の朝、摘出のため手術室に入る夫を家族で見送った。やがて夫の心臓を収めた箱を抱えて外科医らが現れ、静かに一礼した。
思わず「お願いします」という言葉が口に出た。「大切に使わせてもらいます」と声をかけられた。
新幹線の駅へ向かうタクシーに、心の中で「行ってらっしゃい」と呼びかけた。
昼過ぎ、付き添っていたコーディネーターが、「移植された心臓が無事に動き出しましたよ」と伝えてきた。悲しいのに「よかった」と思った。
翌日までに、肺、肝臓、腎臓も無事に移植された。
次回は同じテーマの(下)を書いております。
最後までご覧頂き、
ありがとうございました🙏










